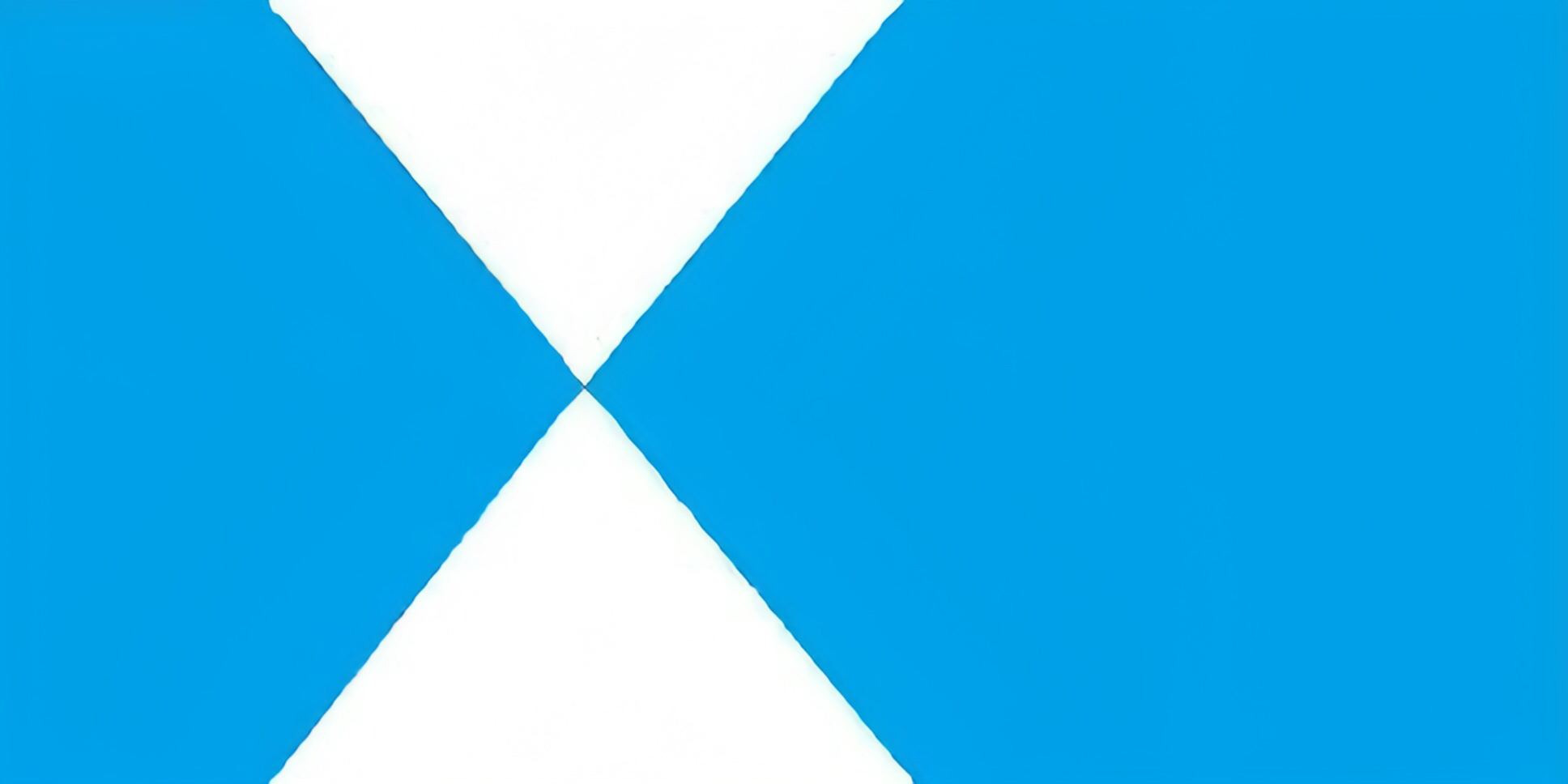1 ベーシックインカムの導入
ベーシックインカム(BI、Basic Income、基本所得) は、政府が全ての住民に無条件で定期的に 一定の金額、所得を給付する政策です。
賛成派は、失業者や高齢者の増加の対策、少子化や経済格差の特効薬として期待します。
しかし切実な生存権の制度化と考える人権派と、コストを削減したくて首切りを簡単にしたい経営側とでは、同じ賛成でも、民衆にとっては全く正反対の結果となる政策になります。
反対論としては「働かざる者食うべからず」という素朴な道徳観や財源の難しさが挙げられます。
「都市連合」では、BI政策の要点を次のように主張します。
(1) BIは 消費が経済を牽引する時代の公共事業である
(2) BIの財源には個人所得税を充てる
(1) BIは消費が経済を牽引する時代の公共事業である
BIは社会保障であるだけでなく、経済政策、公共事業であると考えます。
BIは、ばらまきです。しかし、そのばらまきは生産部門にばらまいた今までの公共投資より、ずっと有効です。それは消費者に直接渡される公共投資だからです。失われた30年、生産や金融への公共投資は景気浮揚策としてほとんど効果がありませんでした。アベノミクスのトリクルダウンも実現しませんでした。末端まで利益が行き渡らないのなら、直接、末端に注入すれば良いというのが、BIを導入せよ、という主張です。
「働かざる者食うべからず」に対しては「食わないと死ぬ」と反論します。現代の経済を牽引しているのは、生産ではなく消費です。生産が足りず働いても食えない時代は、働かないで食う者は非難されたでしょう。しかし、現代は衣食住が余っている時代です。生産側もマーケティングリサーチをして、買ってくれるものを作る時代です。消費者が「食ってくれないと(生産者は)働けない」のです。順番でいえば、まず人々にBIを給付し、消費活動で経済を活性化し、景気を良くする、です。
(2) BIの財源には個人所得税を充てる
BIの財源は個人の収入に対する課税でまかないます。個人の収入の半分、一律50%を所得税として集め、これを全ての住民に平均収入の20%を目安にBIとして配分します。さらに65歳以上の高齢者と障害者等に同額を年金として給付します。(国民負担率は47.5%(2022年度)でさらに上昇中です)
支給方法は、一案ですが、IDを兼ねるICカードで行おうと思います。毎月、ICカードの残高に支給額を上限としてチャージする方法で支給します。ICカードに替えて、生体認証(指の静脈など)を使用することも認めます。雇用主など給与報酬支払者には、毎月、給与を就労者に振込むときに同額の所得税を税務署の口座に振込んでもらい、翌月、この口座から全住民にBIと年金を支給します。
(就労者に課せられる所得税総額)と(BIと年金の支給総額)とが釣り合えばこの財源案は可能です。
就労者数Y、年金受給者数X、総人口A、平均収入M、所得税率(%)a、BIの分配率=対平均収入割合(%)をbとしたとき、aMY=bMX+bMA が成り立てば良いのです。
この式を変形してY=b/a(X+A)とすると、釣り合うのに必要な就労者数を計算できます。aを50%、bを20%とすると、Y=2/5(X+A)となり、高齢者率は2040~60年の40%が頂点ですから、年金受給者数X=0.4A として計算すると、Y=0.56Aとなり、これは総人口の56%が働けば良いということになります。現状は、2023年 現在で、総人口の54%ですから、十分現実的だと思います。